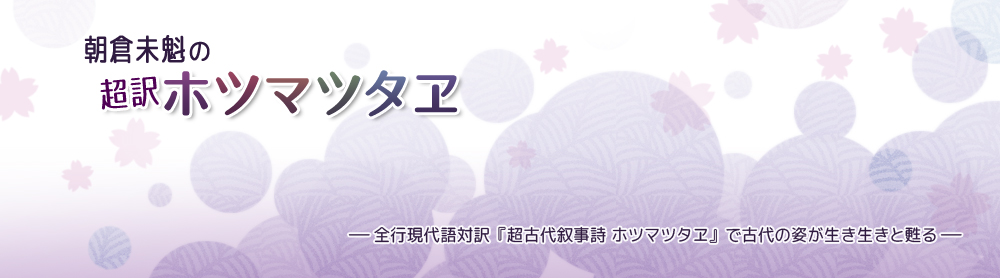先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【オキツヒコ】
13綾本文073以降に出てくる。煮捨竈といわれたが、後に「夫婦和合の教え」を説き、カマドカミという称号を受けた。
【ヒミツ】 和仁估本の漢訳には「秘蜜」とあるが、「ヒ」は火、「ミ」は「ミツ」で水、「ツ」は「ツチ」で土。神々としては本文033以降や087以降に「カグツチの神、ミツハメの神、ハニヤスの神」などと出てきて、火と水と土は人の生活と直結しており、人の生活を助けるとともに脅かすものだったのだろう。
【ヒミツ】 和仁估本の漢訳には「秘蜜」とあるが、「ヒ」は火、「ミ」は「ミツ」で水、「ツ」は「ツチ」で土。神々としては本文033以降や087以降に「カグツチの神、ミツハメの神、ハニヤスの神」などと出てきて、火と水と土は人の生活と直結しており、人の生活を助けるとともに脅かすものだったのだろう。
【ミカマトノカミ】
現代でも竈は単に煮炊きするところだけではなく、その家の生活そのものや身代を意味する言葉として残っている。竈の土と、煮炊きの火と水を合わせて「御竈の神」とされたのであろうか。
【ミツノネ】
「ネ」は音や響きを表す語と考え、「祓い」とした。
| 22-003 |
|
遷宮された時の天の御孫ニニキネの
| 22-004 |
|
詔により御竈の守を賜った
【カシキ】
「カ」は赤、「シ」は白、「キ」は黄色。私はもう一つの解釈として「カシキ」を「炊く(カシク)」の連用形から名詞形になったものとして炊事をすること、飯を炊く人や所をいい、炊殿(カシキドノ)(炊殿は神社で神饌を炊ぐところ)とも考えるが、33綾本文131に「カミノツケ カシキホコタテ カミマツレ」とあり、炊殿とするには整合性を欠くので、「赤白黄」とする。
| 22-006 |
|
幣を持ち、多くの臣達を
| 22-007 |
|
集めて行った。「タカマノハラの
| 22-008 |
|
神司であられるアマテラス
| 22-009 |
|
ヲオンカミが御竈の神を寿ぎ奉った
| 22-010 |
|
祝詞の御言葉は『御竈を寿ぎ奉る
| 22-011 |
|
その神は、天地の開けた
| 22-012 |
|
時に、クニトコタチが
【カンハラミ】
神が孕むのではなく、理念の中に生み出されること。21綾本文111以降に同様のことが書かれている。そこでは現実のものとして意訳をしたが、ここは祝詞の中の言葉としてそのまま使った。
【ヲフヒノミナ】 「ヲフ」は名として持つこと。「ヒノミナ」は「キアヱ、キアト、ツミヱ…」などヱトの60の呼び名。このとき暦はすでにあったようだが、この時代に過去のことについて述べる時、いつからとはっきりしないものは、「アメツチノヒラケシトキ」とか「クニトコタチノ」とかと表現していたのではないか。
【ヲフヒノミナ】 「ヲフ」は名として持つこと。「ヒノミナ」は「キアヱ、キアト、ツミヱ…」などヱトの60の呼び名。このとき暦はすでにあったようだが、この時代に過去のことについて述べる時、いつからとはっきりしないものは、「アメツチノヒラケシトキ」とか「クニトコタチノ」とかと表現していたのではないか。
| 22-014 |
|
キツヲサネのヰクラの神が
【ナナヨノウチノ アマツコト】
「ナナヨ」はクニトコタチからイサナギ・イサナミまでの七代。アマテルカミまでのすべての君は、天の神・地の神にかかわる行事で人々の「御竈」すなわち生活を守るよう祈ったのであろう。
| 22-016 |
|
天の神の祭りで、トホカミ
【ヤモトノカミ】
トホカミヱヒタメの神。このうちのヱとトの神が暦にかかわっており、暦を「ヱト」ともいう。
【クニツマツリ】
地の神の祭り。
【キツヲサネ ムロソヒカミ】
21綾本文022以降に室屋の神々が書かれている。「キツヲサネ」5神と「アミヤシナウ」6神の11神でムロソヒカミ(室神11神)となるのであるから、「アミヤシナウ」が省略されていると考える。ところが、ホツマツタヱの中には「アミヤシナウ」という神の名は一度も出てこない。わずか本文028に「アミヤシナウテ」ということばがあるだけである。6神を「アミヤシナウ」とした根拠は、ミカサフミのタカマナルアヤに「ノチソヒノキミ キツヲサネ アミヤシナウモ アニカエリ」とあることによる。このアマテルカミの祝詞は天地の神に人々の生活を守ってもらうという気持ちが表れている。ついでながらこの後に「コノカミハ ハラワタイノチ ミケオモル ウマシアシガイヒコヂカミ」とあり、「ソヒ神」はマルチな神なのである。
| 22-020 |
|
御竈を守らせた。故にこの神々を日々の
| 22-021 |
|
御竈のヱト守神と
| 22-022 |
|
讃え申すなり』であります。
| 22-023 |
|
久方のアマテルカミが
【ハツミヨ】
アマテルカミは誕生してすぐに即位しているので、生誕の年でもある。
【ヒヨミノトリノ カオツグル】 「ヒヨミノトリ」は暦。「カオツグル」は、「太陽が昇った、光を放った」ということから新しく使われるようになったということと解釈した。陽光とともにアマテルカミが誕生したことと重ねて表しているとも考えられる。
【ヒヨミノトリノ カオツグル】 「ヒヨミノトリ」は暦。「カオツグル」は、「太陽が昇った、光を放った」ということから新しく使われるようになったということと解釈した。陽光とともにアマテルカミが誕生したことと重ねて表しているとも考えられる。
【キツオカナネノ…アミヤシナウテ】
ここはキアヱ暦の構成の仕方の説明。「キツ」は「キツヲサネ」。「カナ」は糸筋。「ネ」は元。「キ・ツ・ヲ・サ・ネ」のそれぞれから「ア・ミ・ヤ・シ・ナ・ウ」のそれぞれに結ぶ。この「キツヲサネ」と「アミヤシナウ」を合わせて「トシノリ神」となる。次に「ア・ミ・ヤ・シ・ナ・ウ」のそれぞれから「ヱ・ト」に結ぶ。その組み合わせはキアヱ、キアト、ツミヱ、ツミト、ヲヤヱ、ヲヤト…と60通りになる。しかしながら「アミヤシナウ」という言葉の意味が今ひとつ解らない。
| 22-026 |
|
「アミヤシナウ」と結び合わせ、それはトシノリ神と
| 22-027 |
|
なりました。そのトシノリ十一神を
| 22-028 |
|
ヱトとそれぞれ結んで編み合わせ、六十組のヱト守神とし、
【ヤミコ】
2綾本文016に出てくる「ヤミコ」はトホカミヱヒタメ。ここでの「ヤミコ」は以下に出てくるヤマサカミのこと。
| 22-030 |
|
それぞれに名前をつけました。
| 22-031 |
|
一番目の名はウツロイの神
| 22-032 |
|
次の名はシナトベの神
| 22-033 |
|
三番目の名はカグツチの神
| 22-034 |
|
四番目の名はミツハメの神
| 22-035 |
|
五番目の名はハニヤスの神
| 22-036 |
|
六番目の名は、稲の豊穣を
| 22-037 |
|
守るヲヲトシ神と
| 22-038 |
|
讃えたものです。七番目の名は水の
| 22-039 |
|
源が豊かに茂るスベヤマズミの
| 22-040 |
|
神で、八番目の末の神は
| 22-041 |
|
「火の鎮め」と津波を鎮める
| 22-042 |
|
タツタ姫です。各々が名前を
| 22-043 |
|
賜って、暦を守る
| 22-044 |
|
ヤマサカミとなりました。
| 22-045 |
|
この神が常に巡って
| 22-046 |
|
守るので、火・水・土に係る
| 22-047 |
|
災いはありません。災いがなければ