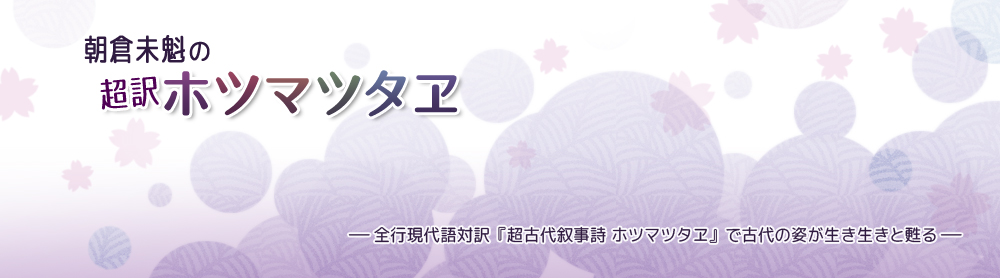先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【アノメツケ コレアタイラゾ】
「メツケ」は室町幕府以降、非違を検察し、主君に報告した監察官とされるが、その原形はすでにこの時代にあった。大辞林に「アタイ」は「直」。「古代の姓の一つで、国造に与えられた」とある。
| 23-198 |
|
物部を八百人束ねる
| 23-199 |
|
主は大物主である。
| 23-200 |
|
補佐役の連と事代主とに
| 23-201 |
|
補佐をさせる。補佐の二人は
【ヘトカサリ】
解釈ノート128で書いたことから、2種類の綜絖で模様を作るように、二人が世の中の秩序を保つ大事な役割だということ。
| 23-203 |
|
機の主に例えられる。それにより、正邪を判断するのである。
【ソノガマデ】
7綾本文163では「ガ」は「罪」で、刑罰の程度は「クラ」。ここでは刑罰の程度も「ガ」となっている。この他にも見受けられるが、ホツマツタヱの表現は時代が進むにつれて変化している。「ガ」の意味に該当する漢字がないので「ガ」のままとする。
| 23-205 |
|
組の者を呼び、十ガ以内なら叱責とする。
| 23-206 |
|
十ガを越える場合は県主に訴える。
| 23-207 |
|
県主は九十ガ以内であれば杖打ちの罰を与える。
| 23-208 |
|
九十ガ以上の罪は牢屋に入れ
| 23-209 |
|
国造(宮の目付け)に訴える。宮の目付けが調べ、
【ケタノガ】
「ケタ」は四角いさま。ここでは四半分。罪の程度を1年の日数の365としたことは本文098に出てきたが、区切り方を見ると、それを円に描いて見ていたようである。そうすると概ね四分の一は91、二分の一は182、四分の三は273となる。しかし最小単位を十ガとしているので端数は省いて考えてもよいだろう。
| 23-211 |
|
追い払う。百八十ガになれば
| 23-212 |
|
国から追放する。百八十ガ以上になると大物主に知らせ、
| 23-213 |
|
大物主が糺して罪を明らかにし、
| 23-214 |
|
二百ガになったら島流しにする。
| 23-215 |
|
二百七十ガになると髪の毛と爪を抜いて
| 23-216 |
|
入れ墨をする。ガの巡りを一回り(三百六十五ガ)すれば
| 23-217 |
|
死罪にする。人を殺す刑罰は
| 23-218 |
|
大物主の判断を受けよ。
| 23-219 |
|
物部等よ、しかと聞け。
| 23-220 |
|
おのれの判断のみで民を斬ってはならぬぞ。
| 23-221 |
|
民はみな、それでも吾の孫同然なのである。
| 23-222 |
|
その民を守り、国を治める
【クニカミ】
クニの中に複数ある県の県主を総称してクニカミと呼んだと考える。
| 23-224 |
|
であるからクニカミは民の父母なのである。
| 23-225 |
|
その民は、クニカミの子どもということになるのだ。
| 23-226 |
|
たとえ我が子でも、親が子どもを斬ってはならぬ。
【ワガコサス】
「サス」は「刺す」と読めるが、傷つけることとした。
【ツミモヤソクラ】 この綾では刑罰の程度は「ガ」なのだが、ここだけ従前の「クラ」となっている。おそらく音数の関係で「クラ」としたのだろう。
【ツミモヤソクラ】 この綾では刑罰の程度は「ガ」なのだが、ここだけ従前の「クラ」となっている。おそらく音数の関係で「クラ」としたのだろう。
| 23-228 |
|
養子を傷つける罪は二百七十クラ、
| 23-229 |
|
妻を傷つける罪は二百七十クラ、
【ウマヅメハ ヨソメゾ】
この文は、前行の「イモイサス ツミフモナソガ」の続きで、「妻を殺す罪は270ガだが、子どもを産んでいない妻は他人の女として扱うので、罪は270ガではない」ということと解釈した。ここでの刑罰についてはすべて親族間のことなので、この場合は他の基準で裁くということか。
【アニモ セモカラス】 「アニ」はすぐ後に説明されているように、子どもがいる夫をいい、いない場合は「セ」と呼んだ。このような区別は今日では考えられない基準である。
【アニモ セモカラス】 「アニ」はすぐ後に説明されているように、子どもがいる夫をいい、いない場合は「セ」と呼んだ。このような区別は今日では考えられない基準である。
| 23-231 |
|
夫を殺す罪は三百六十ガ、
| 23-232 |
|
妻に子がいない夫はヨソ(他人の男)といい、子がいればアニ(夫)という。
| 23-233 |
|
父母を殺す罪は三百六十ガ
| 23-234 |
|
義父母を殺す罪は四百ガである。
| 23-235 |
|
世の規範を民の一組(五軒)が
| 23-236 |
|
乱しても、筬で横糸を揃えられず
| 23-237 |
|
機が織れなくなるように世の秩序が保てなくなる。それ故に世を治める則は
| 23-238 |
|
『機織の則』そのものなのである」。
| 23-239 |
|
するとまた、大物主が
| 23-240 |
|
聞いた。「昔は世の中が乱れていなかったし
| 23-241 |
|
人々は奢った暮しをしていなかったのに、無法者への罰則は
| 23-242 |
|
どうしてできたのですか」。するとアマテルカミは笑みを浮かべて答えた。
| 23-243 |
|
「汝は元々単純に考えるが、
| 23-244 |
|
今後、大変世の中が治まって
| 23-245 |
|
飢えを知らず、奢った暮しを楽しむ風潮が
【ウヱトシゴロハ】
「ウヱトシ」を飢える年と解釈し、「不作の年」とした。
| 23-247 |
|
稲が実らず、真に飢えてしまうのだ。
| 23-248 |
|
このことから、予め定めてある『衣の則』に