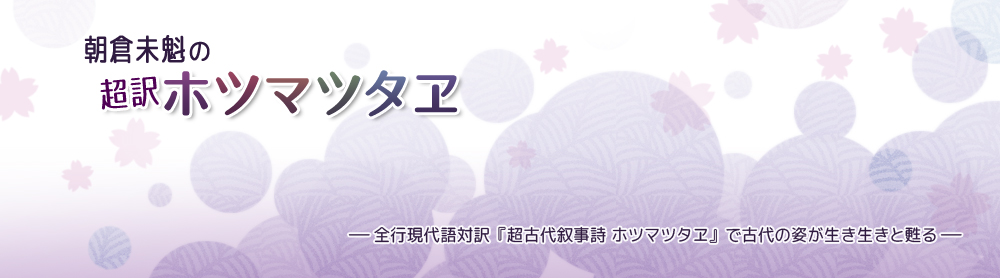先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【モモソヒメ オオモノヌシノ ツマトナル・・・・】
大物主はすでに神なので、「ツマ」になったと言っても「妻」ではない。ここの話は歴史的な実話とは考えられないが、何かの事実が裏に秘められていると考える。ここから「コシガテンカモ」までを、「ハシ塚」(箸墓古墳?) に祭られているモモソ姫にまつわる出来事として想像をめぐらした。以下は私の想像する「事実」である。
「モモソ姫は大物主神に仕える巫女となった。モモソ姫にはすでに恋人がいて、夜になると忍んで逢っていた。ある朝、大物主の末裔で、大三輪の神の祝主でもあるオオタタネコがモモソ姫を訪ねてきた。いてはならない男を目撃したオオタタネコは慌てて用件も告げず帰ってしまった。モモソ姫は神に仕える巫女として大いに恥じ、自ら命を絶ってしまった。それを知った多くの人の哀惜の情が箸塚をつくらせた。」
「クシゲ(櫛箱)」を女性のいる部屋、「コヘビ(小蛇)」を男性とするとモモソ姫の部屋に男がいたことを暗示していると思われる。「ヒメオドロキテサケビナク」はモモソ姫がオオタタネコに見つかって狼狽する様子。オオタタネコは、モモソ姫が仕えている大物主の末裔なので、オオモノヌシに見つかったのと同じような恐怖を感じたのではないか。オオタタネコが踵を返したのは、モモソ姫に気を使ったのかもしれないが、モモソ姫にしてみれば「ナンヂシノビズ ワガハジト オオゾラフンデ」帰って行ったと思われたであろう。恥、後悔、恐怖、それらのために絶命したのか、自死したのか、死んでしまったのである。 (それでも、自分の陰部を突いて死ぬことはありえないし、尻餅をついて箸が陰部に刺さるなんて状況があるわけないと私は思う。)
オオタタネコはモモソ姫の気の毒な死を悼み、塚を造ることにした。この頃エビス討伐で多くの犠牲者も出たので、その者たちも合わせて「オレガレ」すなわち生を全うできずに死んだ人の大きな塚を造った。そこで、オオタタネコは「ヲトクマツリ」を祭主として行ったのである。以上のような解釈だが、本文は人々の間に生まれた物語の通り訳した。
「モモソ姫は大物主神に仕える巫女となった。モモソ姫にはすでに恋人がいて、夜になると忍んで逢っていた。ある朝、大物主の末裔で、大三輪の神の祝主でもあるオオタタネコがモモソ姫を訪ねてきた。いてはならない男を目撃したオオタタネコは慌てて用件も告げず帰ってしまった。モモソ姫は神に仕える巫女として大いに恥じ、自ら命を絶ってしまった。それを知った多くの人の哀惜の情が箸塚をつくらせた。」
「クシゲ(櫛箱)」を女性のいる部屋、「コヘビ(小蛇)」を男性とするとモモソ姫の部屋に男がいたことを暗示していると思われる。「ヒメオドロキテサケビナク」はモモソ姫がオオタタネコに見つかって狼狽する様子。オオタタネコは、モモソ姫が仕えている大物主の末裔なので、オオモノヌシに見つかったのと同じような恐怖を感じたのではないか。オオタタネコが踵を返したのは、モモソ姫に気を使ったのかもしれないが、モモソ姫にしてみれば「ナンヂシノビズ ワガハジト オオゾラフンデ」帰って行ったと思われたであろう。恥、後悔、恐怖、それらのために絶命したのか、自死したのか、死んでしまったのである。 (それでも、自分の陰部を突いて死ぬことはありえないし、尻餅をついて箸が陰部に刺さるなんて状況があるわけないと私は思う。)
オオタタネコはモモソ姫の気の毒な死を悼み、塚を造ることにした。この頃エビス討伐で多くの犠牲者も出たので、その者たちも合わせて「オレガレ」すなわち生を全うできずに死んだ人の大きな塚を造った。そこで、オオタタネコは「ヲトクマツリ」を祭主として行ったのである。以上のような解釈だが、本文は人々の間に生まれた物語の通り訳した。
| 34-053 |
|
ツマになった。大物主に「夜はいらっしゃいますが
| 34-054 |
|
昼にはお姿を見られません。夜が明けても君の
| 34-055 |
|
お姿を見たいです」と留めると、
| 34-056 |
|
大物主が言った。「それは全く言うとおりだ。
| 34-057 |
|
我は明日の朝、櫛箱に入っていよう。
| 34-058 |
|
我の姿を見ても、決して驚かないように」と言った。
| 34-059 |
|
モモソ姫は不思議に思って
| 34-060 |
|
あくる朝櫛箱を開いて見ると、
| 34-061 |
|
そこには小さな蛇が入っていた。モモソ姫は驚いて
| 34-062 |
|
泣き叫んだ。大物主は恥をかいたと
| 34-063 |
|
人の姿に戻ると「汝は我慢することができず
| 34-064 |
|
我は恥をかいた」と言って大空に向かい
【ハヂツキオルニ】
「ツキ」は極限に達する、「オル」は動作・状態の継続を表す「―している」と解釈した。「ひどく恥じた状態が続いていることとして、「恥ずかしさに身悶えして」と意訳した。
【ハシニミホドオ ツキマカル】
記紀では自ら「ほと」を突いて死んだことになっているが、到底そのような死に方を選ぶとは思えない。ここでは「ハシ」は「愛し」と読み、いとしいこととした。「ミホド」の「ミ」は身、「ホド」は限り、「ツキ」は「尽き」と読み、「哀れにも身命の限りが尽き果てて命絶えてしまった」と意訳した。
| 34-067 |
|
付き果てて命絶えてしまった。モモソ姫の亡き骸はオイチに葬り、
【ハシツカ】
「ハシ」は「愛し」と読み、愛しい方(モモソ姫)を指し、愛しいモモソ姫が眠る塚。「倭迹迹日百襲姫大市墓」とされている纏向遺跡の箸中古墳群のひとつの箸墓古墳ではないか。
【ヨハカミノ】
「夜は神の」と読めるが、何を意味しているのか不明。人々の熱心さで、人の働けない夜には神も手伝ってくれたと思われる速さで出来上がったのだろうか。「神」とは、モモソ姫を不憫に思った大物主のことと思っているのか。
| 34-070 |
|
石を運んだ。人々が次々に
| 34-071 |
|
手渡しをして墓ができあがった。その時みなが歌った歌
【ツキノカオソヱ】
「次の顔添え」と読み、次の人へ振り向きながら手渡しする様子と解釈した。
| 34-073 |
|
多くの石を手から手に運んでいると
【コシガテンカモ】
「コシ」は「タコシ」(手越し、手から手に渡すこと)の「コシ」、「テン」はカガンノンテンの「テン」。神事の時に打つ太鼓。
| 34-075 |
|
十一年四月十六日、四人の教え人が
【エビス】
都から遠く離れた土地の人。未開の地の荒々しい人々。ここでは、コシ、ホツマ、ツサ、タニハを指す。
| 34-077 |
|
国は平穏になった。秋にオオタタネコに
【オレカレノ ヲトクマツリオ ハシヅカニ】
「オレカレ」は「折れ枯れ」と読み、命が途中で折れて死ぬこと、すなわち不慮の死、生を全うすることなく死ぬことと解釈した。この文の前に「オレカレ」したのは兵士の他にモモソ姫もいる。「ヲトクマツリ」を箸塚で行う理由として本文052からのモモソ姫のエピソードが書かれているのではないか。まさに箸塚は「ヲトクマツリ」にふさわしい場所なのである。
【カカヤク ノリノイチ】
訳では「祭り」としたが、「ノリ」は緒を解く「法」。「イチ」は「市」、人の大勢集まる場所と考えた。こういう機会に物々交換などが行われたのではないか。
| 34-080 |
|
緒を解く祭りの場として人々が集まった。十二年三月十一日に
| 34-081 |
|
詔があった。「君の御位を
【アメノオフヒ】
「オフヒ」は「覆い」とよみ、空を覆っている状態とした。
【メヲアヤマリテ】
天地の原則が狂うこと。
| 34-084 |
|
季節がうまく巡らなくなった。疫病がはやって
| 34-085 |
|
民は病気になった。罪を払おうと
【アラタメテ】
「改めて」と読むと、今までより一層神を敬うことと解釈できるが、ミマキイリヒコ(崇神天皇)の時代に数多くの神社が造られたことから、「新たに社(神社)を造り」とした。
【ヤヲノアラビト】
「 」は池田満氏の解釈によれば「メには見えないつながりのヲ」。ここではある働きをするものの範疇のように考え、仲間ではないが「同類の輩」のような意味と解釈した。
」は池田満氏の解釈によれば「メには見えないつながりのヲ」。ここではある働きをするものの範疇のように考え、仲間ではないが「同類の輩」のような意味と解釈した。
| 34-088 |
|
今は従って、全ての人が楽しく暮らせるようになった。
| 34-089 |
|
そこで吾は次のように考えて政を行った。長幼の
| 34-090 |
|
序を守らせ、民に負わせる
【ユハズタズエノ ミツギ】
「ユハズ」は広辞苑に「ゆはずのみつぎ(弓弭の調)、男子人頭税。弓矢で獲った鳥獣が主な貢納物だったからいう」また「タズエ」は「たなすえのみつぎ(手末の調)、女子が布帛を織って献じた物」とあるのでそのことだろう。
| 34-092 |
|
貢をやめた。民の生活にゆとりを持たせて
| 34-093 |
|
稲の収穫も元通りになって安心した。
【ハツクニシラス ミマキノヨ】
ミマキイリヒコ(崇神天皇)は、古事記では「所知初國之御眞木天皇(ハツクニシラシシミマキノスメラミコト)」、日本書紀では「御肇國天皇(ハツクニシラススメラミコト)」と名乗ったとなっている。また、タケヒト(神武天皇)も、日本書紀に「始馭天下之天皇(ハツクニシラススメラノミコト)」とあり、微妙な言葉の違いはあるが表記からは二人とも初めの天皇であると受け取れる名前で、研究者の間でも明解な説はない。ミマキイリヒコ(崇神天皇)は、詔の中で天皇の位を引き継いだことを述べているので、自分を初代などと名乗るとは考えられない。「ハツ」を「初」と読むとすると、「初めの国のように領らした(建て直した)」と解釈でき、「果つ」と読めば「果つ国領らす」、すなわち、「いったん果てようかというほどの惨状から国を立て直した」という意味と考えられる。日本書紀の表記を見ても「御肇國」の「肇」は、「はじめて・はじめる」の他に「ただす・ただしくする」の意がある。「ただす」とすると、日本書紀でも国を建て直した天皇と考えていたということになる。日本書紀の表記を読み取れず、崇神天皇を「初代」のように解釈してしまったところから混乱が生じたのだろう。また、タケヒト(神武天皇)の名前「始馭天下之天皇」の「馭」は「馬を操り走らせる」の意なので、名前の意味を考えると「馬を操り走らせ、国を初めて拓いた天皇」となる(実際は船で乗り降った)。これは、18綾本文029、アメミヲヤが「クニタマオ ノリメグリ」オノコロを創った。同044、クニトコタチも「ノリメグリ クコワニヤモオ ナニガタト ウムクニスベテ オノコロゾ」、同064、「フタカミノ ツギテアマネク ノリメグリ・・・タミモヰヤスク ナスクニオ オノコロジマト ナツクナリ」と、大事な国造りの場面で「ノリ」巡って治めている。「馭」にその意味が込められており、神武天皇が初代の天皇ということを表わしているのではないか。
| 34-095 |
|
ミマキの代とする」。民が楽しく暮らしたので