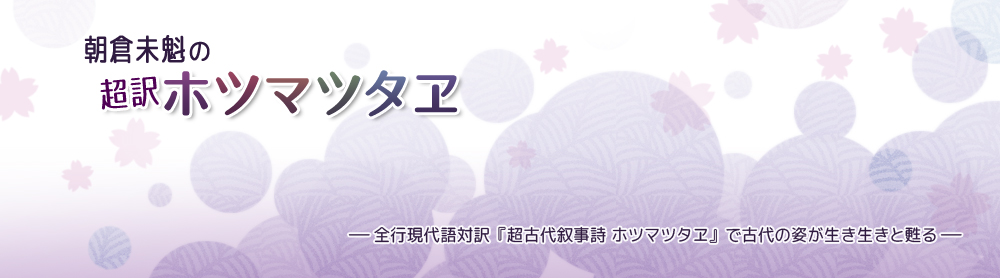先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【キサキモオエテ】
「オエテ」が意味不詳。「生えて」くらいしか読めず、ここでは、この後の記述に合わせて「妃の御子も生まれて」と解釈、訳は妃を主語とした。
| 34-097 |
|
スケ妃のヤサカ姫がトイチに行ったとき
| 34-098 |
|
産んだ皇女はトチニイリ姫である。
| 34-099 |
|
二十六年十一月一日に
| 34-100 |
|
ミマキ姫が磯城で産んだ皇子は
| 34-101 |
|
トヨキヒコ、諱シギヒトである。
| 34-102 |
|
二十九年一月一日、ヲウトに
| 34-103 |
|
后がまた産んだ皇子はイクメ
| 34-104 |
|
イリヒコ、諱ヰソサチである。
| 34-105 |
|
三十八年秋、八月五日に
| 34-106 |
|
后の妹でウチ妃のクニカタ姫が
| 34-107 |
|
産んだ皇女はチチツクワ姫である。
| 34-108 |
|
四十年一月二十八日に産んだ皇子は
| 34-109 |
|
イカツル、諱チヨギネである。
| 34-110 |
|
四十八年一月十日、ヲアエに
| 34-111 |
|
君がトヨ君(トヨギヒコ)、イクメ君(イクメイリヒコ)とに
| 34-112 |
|
言われた。「汝たちへの愛情は
【ツギシルコトノ ユメスベシ】
夢と言っても、「将来の夢」すなわちビジョンを考えろということであろう。
| 34-114 |
|
夢を見よ」。二人とも身を清めて
| 34-115 |
|
夢を見た。トヨギヒコが言った。
| 34-116 |
|
「三諸山の上で東を向いて八度
【ホコユケシ】
この場面の他に「ホコユケシ」の解釈のヒントになる記述がなく、広辞苑に「ホコユケ」として「矛をあやつって突きやること」とあるのみだが、出典は崇神紀。「ヤタビ」と続いているので、この解釈で間違いないだろう。
| 34-118 |
|
「三諸山の上で四方に縄を張り
| 34-119 |
|
雀を追う夢を見ました」。君は二人の夢を
| 34-120 |
|
比べて考え、「兄の夢はただ
| 34-121 |
|
東を向いているだけなので、東国のホツマを治めさせることにする。
| 34-122 |
|
弟の夢は四方に向かっているので民を治める
| 34-123 |
|
世継ぎとする」と言われた。四月十九日ツミエに
| 34-124 |
|
詔を下し、ヰソサチを
| 34-125 |
|
世継ぎ皇子とした。トヨギイリヒコは
| 34-126 |
|
ホツマ司とした。
【ミマナノアヤ】
なぜ、わざわざ「任那の綾」と章立てして挿入されているのだろうか。外国の話だということだからだろうか。何かその他に理由があるのだろうか。「コレノサキ」以降の挿話も前後とどのようなつながりがあるのか分からない。面白い話があったので区切りの所へ挿入したのだろうか。
| 34-128 |
|
ミヅカキの五十八年八月に
| 34-129 |
|
ミマキイリヒコは行幸して食飯大神に
| 34-130 |
|
参拝された。諸臣が神を祝っている時
| 34-131 |
|
角が一つの被り物を被った人が海岸に
| 34-132 |
|
船で漂着した。言葉が何を言っているのか分からなかった。
【ソロリヨシタケ ヨクシレバ】
みなが分からない、漂着したカラ国の言葉を知っているということは、ソロリヨシタケは渡来人であろう。
| 34-134 |
|
その言葉をよく知っているので、ソロリヨシタケに聞かせた。
| 34-135 |
|
その人は「我はカラ国の
| 34-136 |
|
君の王子で、ツノガアラシトといいます。
| 34-137 |
|
父の名はウシキアリシトです。
| 34-138 |
|
伝え聞いている聖の君に
【アナト】
関門海峡の古称、または長門の国の古称。
| 34-140 |
|
ヰツツヒコが我に言うには、
| 34-141 |
|
『この国の君は我である。
| 34-142 |
|
ここにいなさい』ということでしたが、その人の様子を見ると
| 34-143 |
|
君のようではありませんでした。いったん帰って、改めて
| 34-144 |
|
都へ行こうと、浦や島を訪ねて
| 34-145 |
|
出雲を経てやっとここに着きました。
| 34-146 |
|
神祭りがおこなわれていて、ここにおられるのが君だと分かりました」。
| 34-147 |
|
そこで、ツノガアラシトを召して使うと
| 34-148 |
|
忠実に働いたので五年目に
| 34-149 |
|
「ミマナ」という名を授けた。たくさん積み上げた錦を