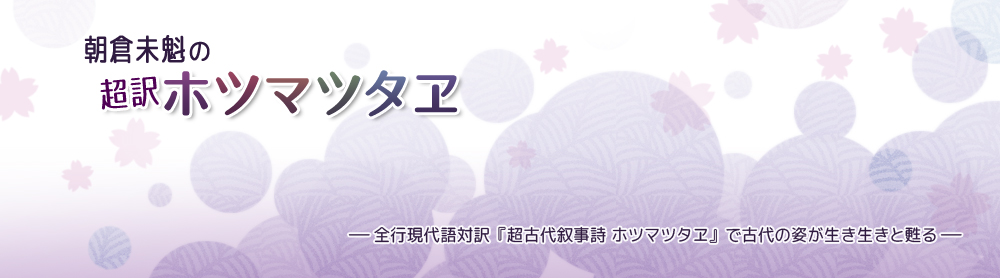先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【カフリミハ】
「ミハ」の「 」は着物を表すので「御衣」とした。この後にも「ミハ」があるが、それぞれ特別な役を持っている者が着ていることから、そのような役の者が着る特別な衣裳ではないかと考える。
」は着物を表すので「御衣」とした。この後にも「ミハ」があるが、それぞれ特別な役を持っている者が着ていることから、そのような役の者が着る特別な衣裳ではないかと考える。
| 40-211 |
|
臣が八人付いた。オシヤマスクネは
| 40-212 |
|
冠と御衣を着け、世掃花を持ち
| 40-213 |
|
臣が六人付いた。キビタケヒコも
| 40-214 |
|
同じように世掃花を持った。オオタンヤワケも
| 40-215 |
|
冠と御衣を着けて剣を奉げ
【ミコシアオホヒ】
「ア」は「天」、「オホヒ」は「覆い」すなわち、上にかぶせる覆い。
| 40-217 |
|
長となった臣が、下僕三十人に御輿を運ばせた。
【ミヲズエ】
「御緒末」。御輿に付けた紐をつかんで歩いたのだろう。昭和になっても、神輿に綱をつけて、大勢の子どもがそれをつかんで歩くしきたりも残っていた。
| 40-219 |
|
四丈八咫の長さがあり、御子達はその御緒末を
| 40-220 |
|
持って歩く。これはアマテル神の時から
| 40-221 |
|
続いているしきたりである。斎主の勅使は
| 40-222 |
|
臣を十二人従え、その次に御幸を守る
| 40-223 |
|
諸々の従者が続き、みなで送って
| 40-224 |
|
夜中まで歩いた。そのようにして六夜かけて
【オホマノトノ】
31綾069に「ホホマノオカ」という似た言葉が出てくるが、そこは奈良県。この「オホマ」は愛知県なので別。ヤマトタケのために建てた宮なのは間違いないだろうが、どういう意味を持っているのかは不明。
| 40-226 |
|
御輿が着いた。ヤマトタケ君が生きているかのごとく、
| 40-227 |
|
ミヤズ姫は切火で火を起こし炊いた粥を
【ヒラベ】
「ベ」は甕(カメ)。平たい甕ということは、平鉢か平椀のようなものか。
| 40-229 |
|
オホマの殿に入って待った。ヤマトタケ君の霊の前に供え
| 40-230 |
|
話された。「この御饌は以前
| 40-231 |
|
伊吹山から帰られたら差し上げようとしたものです。
【ヒルメシ】
昔は1日2食だったという説が多いようなので「昼飯」でいいのだろうか。本文161でミヤズ姫がヤマトタケを「タカヒカル アマノヒノミコ」と呼んでいるので、私は「ヒ (ノミコ) 」の「ル(霊)」に奉げる御飯と解釈した。すでに亡くなっているヤマトタケへの御飯なので、君への最高の敬意を以て飯に「ヒル」を付けたのではないか。
| 40-233 |
|
お待ちしましたが、君は私のもとに寄らないで行ってしまわれました。
| 40-234 |
|
とても残念でしたが、今また
| 40-235 |
|
君は神となって来てくださいました。是非お召しあがりください。
| 40-236 |
|
まだ御存命の時のアイチ田でお待ちしていた
| 40-237 |
|
君のために心を込めた御饌なのです」と
| 40-238 |
|
三度申し上げると、十六夜の月が
【シライトリキテ…】
原文に合わせて訳したが、白い大きな鳥が米の飯を食べ、ツヅ歌が聞こえてくるというのは実際にはあり得ないことなので、私は「白い鳥の羽をヤマトタケの変身の証しと考え、儀式の中でこのような場面を演じた」と解釈した。ツヅ歌もヤマトタケの気持ちを詠んだ歌と考えた。
| 40-240 |
|
御饌を食べると、白い雲の彼方に消えていった。
| 40-241 |
|
そしてヤマトタケ君のツヅ歌が聞こえてきた。
| 40-242 |
|
「この世にいた時にハラ宮(オホマの殿)で食べたかった
【チリオヒルメシ】
ここでの「ヒル」は「箕で穀物をふるって、風でくずを取り去ること」とし、ミヤズ姫が米の汚れを取り去り炊ぐまでしたことと、姫の純粋な気持ちを掛けて表していると考えた。
| 40-244 |
|
霊妙な儀式に、みなはまことに畏れ多く思い
【オホマノトノヨリ ミヤウツシ】
オホマの殿は、ヤマトタケがミヤズ姫と住みたいと願った宮であり、ヤマトタケの死後に建てられたので、建てたときに御霊を祀る祭殿も造ってあったのではないか。
| 40-246 |
|
祭殿へヤマトタケの御霊を遷し、勅使が幣と
| 40-247 |
|
皇の言葉を申し上げた。この時勅使の
| 40-248 |
|
タタネコとオハリムラジが、
| 40-249 |
|
ヤマトタケ君に「新ハラ宮のオホマの神」と
| 40-250 |
|
名付けた。亡くなった人を葬送するとき
| 40-251 |
|
供える御饌は「世を辞むチリヒルメシ」と
| 40-252 |
|
して伝えられた。伊勢に連れて行った
| 40-253 |
|
蝦夷の五人は、アマテルカミを敬わなかったので
| 40-254 |
|
ヤマト姫はそれを咎めてミカドの所に
| 40-255 |
|
行かせた。その五人を三諸山に居させると
| 40-256 |
|
間もなく木を伐って、民を
| 40-257 |
|
困らせた。君は
| 40-258 |
|
「蝦夷達はヤマトの人と考え方が違うので
| 40-259 |
|
ここには置いておけないから、それぞれ分けて置く」と言われた。
| 40-260 |
|
これが播磨、安芸、阿波、伊予、讃岐の