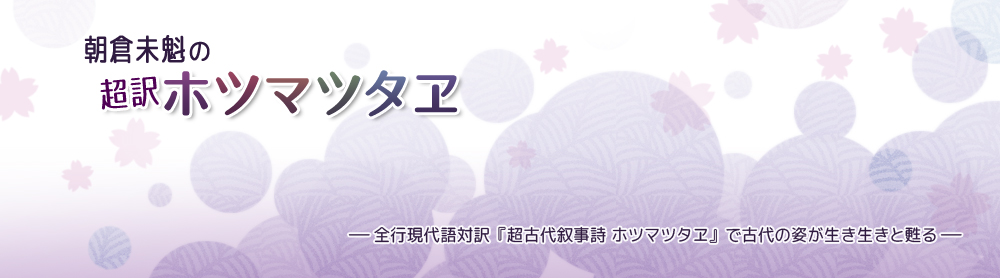先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【ミハサダメ】
位によって着る物を定めること。今日でも天皇即位など皇室の重要な行事では、天皇や皇太子などの着るものの色などに決まりが残っている。
| 23-001 |
|
あまねく世の中が穏やかに
| 23-002 |
|
治まっているある日、多くの物部達が
【シラヰシ】
宮の庭に白い玉砂利のようなものが敷かれていたのであろう。
| 23-004 |
|
大物主が「人を斬る物が宝とされているのは、なぜですか」
| 23-005 |
|
と訳を聞いた。するとアマテルカミが
| 23-006 |
|
話された。「この剣の元は
| 23-007 |
|
昔君が使っていた矛である。クニトコタチ尊の
| 23-008 |
|
時代にまだ矛がなかった訳は
| 23-009 |
|
人は心が素直で、則を守っていたので
| 23-010 |
|
矛は要らなかったのだ。人々は心根が真っ直ぐで
| 23-011 |
|
クニトコタチ尊の時代には億万歳もの
| 23-012 |
|
寿命だったのが、ウビチニ尊の世になると
| 23-013 |
|
仰々しく心を装っていたので
| 23-014 |
|
寿命は百万歳となった。
| 23-015 |
|
オモタル尊の世は民がずる賢しくなって
【オノモテキリヲサム】
「斧で切る」ということは刑罰によってということ。
| 23-017 |
|
斬って国を治めた。斧は木を切る
| 23-018 |
|
道具なので、鍛冶師に矛を
| 23-019 |
|
作らせて、ずる賢い者を斬ったため
| 23-020 |
|
オモタル尊の世継ぎがなくなり、民の寿命も
【ヤヨロナレ】
「ナレ」は均して。平均。
| 23-022 |
|
昔、一万歳の寿命だったのが縮まって
| 23-023 |
|
百歳になり、また一万歳になったということがあった。
【コレススオ ムスブカミナリ】
自然の成り行きを言っているものと思われるが、この時代は心が清ければ長生きし、心が穢れていれば早死にすると信じられていた。これがいつの時代のことをいっているのかは不明。
| 23-025 |
|
恐ろしいのは、罪のない人を斬ると
【ゲニツツシメヨ】
話している相手の物部は、今でいう警察のような役割だから強調したのだろう。
| 23-027 |
|
オモタル尊に世継ぎがなく、政を
| 23-028 |
|
継ぐ者がいなくなりそうになった。そこでオモタル尊がイサナギ尊に
【トヨアシハラ】
辞書には日本国の美称とあるが、ここでは琵琶湖の辺りと考えられる。2綾本文073に同じことが書かれているが表現が違う。ここはその結果として田が拓かれ「豊葦原」になっているのでこのような表現になったのだと考える。
| 23-030 |
|
広く開けて稲田になる土地がある。
| 23-031 |
|
汝が行って治めよ』と、
| 23-032 |
|
トと矛を授けられた。
| 23-033 |
|
トは法を定めた文(フミ)、矛は逆矛である。
| 23-034 |
|
二尊はこれを使って
| 23-035 |
|
アシハラで国固めを終えた。
【ヤヒロノトノト ナカハシラタテテ】
そこを政治の中心地とした。
| 23-037 |
|
中柱を建てて国々を巡ったので、
【オオヤシマ】
日本国の古称。
| 23-039 |
|
トの教えが行き渡った。広い土地の葦も
| 23-040 |
|
全部抜いて田としたので、民も
【ヰヤマト】
「ヰヤ」を「弥」の意の「ますます」とした。「マ」は真の、「ト」はトの教え。
| 23-042 |
|
国の名もヤマトの国となった。真のトの教えは
| 23-043 |
|
昇る日のように栄えるもととなったので
| 23-044 |
|
ヤマトの国を『日の本』と呼ぶようになった。しかし、ヤマトの
| 23-045 |
|
名前を忘れてはならない。吾はトの道によって
| 23-046 |
|
国を治めているのでオミ(臣)もトミと呼ぶのだ。
| 23-047 |
|
その訳は次のとおりである。モトアケの
| 23-048 |
|
ミヲヤカミがおられる後ろには
| 23-049 |
|
北の星(北極星)があり、今、天上には