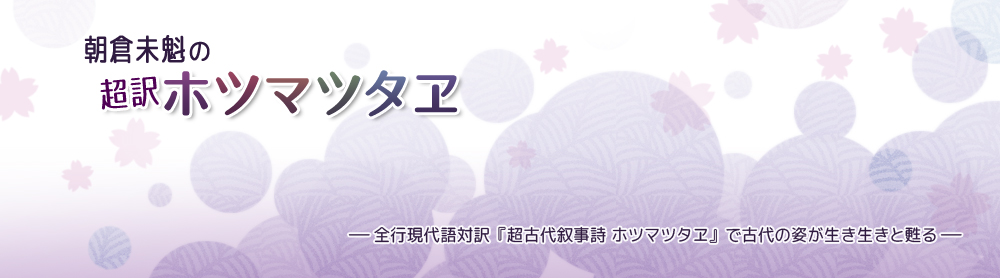先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【ミソムメノ トノカミヰマス】
「36代目のトの神」とは誰か。この文の前で二尊がトの教えで国を栄えさせたことが書かれ、この後でもトの教えについて述べており、「ナカハシラ」が立っているとも書かれているので、トの教えで国を治めた二尊を指していると考える。私は二尊が36代目であるということまでは分からないが、アマテルカミは36代目であることを知っていたのであろう。
【ナカハシラ】
天より地上につながっていて、神から与えられるものが降りてくる柱のようなものがあると信じられていた。
| 23-052 |
|
吾が、国を治める道理は天より下された
【トノカミト】
和仁估本では「 (ト) 」と「
(ト) 」と「 (ノ) 」を重ねたようなホツマ文字となっていて「ノ」とルビが振ってあるが、文脈からすると「
(ノ) 」を重ねたようなホツマ文字となっていて「ノ」とルビが振ってあるが、文脈からすると「 」と考えられる。
」と考えられる。
| 23-054 |
|
守ったので、吾の心と人々の心が
| 23-055 |
|
共感し、すべての人々の心がまとまったのだ。
| 23-056 |
|
トの教えは、長く国が治まる
| 23-057 |
|
宝である。君の位を
| 23-058 |
|
引き継ぐ日に受ける三種の神宝の
【アメナルフミ】
トの教えのこと。
| 23-060 |
|
奥義はこれである。
| 23-061 |
|
また矛も宝だという訳は次のとおりである。
| 23-062 |
|
トの教えで国を治めても
| 23-063 |
|
人々の中にいる邪悪なことに敏い者は
| 23-064 |
|
自分に合わなければ道理に
| 23-065 |
|
従わないで逆らう。一人が道に叛けば
| 23-066 |
|
仲間を増やし、群れ集まって
| 23-067 |
|
不平不満を言う。トの教えを妨げる者がいれば
| 23-068 |
|
召し捕り、糺して罪を明らかにし
| 23-069 |
|
罰する。矛は国を治める道理を
【ミタレイト】
乱れた糸。本文123以降に政治を機織りに例える話が出てくる。
| 23-071 |
|
道具である。天下の道理に
| 23-072 |
|
逆らうと、その身に受けることになる天の
| 23-073 |
|
逆矛(刑罰)なのである。国が乱れると
| 23-074 |
|
田も荒れて稲穂も実らず
| 23-075 |
|
民が貧しくなるが、罪人を斬って
| 23-076 |
|
民が田を耕せるようにすれば、稲穂が実って
| 23-077 |
|
民は豊かになるのだ。収穫したものをオオトシ神に
| 23-078 |
|
奉げることができれば国中が賑わう。
| 23-079 |
|
稲穂は田から出たものであるから宝というのだ。
| 23-080 |
|
逆矛も罪人を討って国を治めるので
| 23-081 |
|
宝なのである。かつてイサナミ尊は言われた。
【アヤマタバ ヒヒニチカフベ コロスヘシ】
5綾本文070の「カクナサザラバ チカフベオ ヒビニクビラン」を引用しているが、ニュアンスが違う。アマテルは自分の教えの文脈の中でわかりやすく言い換えたのであろう。
| 23-083 |
|
殺すことになるでしょう』すると、イサナギ尊も言われた。
| 23-084 |
|
『麗しい人よ。吾は千五百人の民を
| 23-085 |
|
増やしましょう』と言って、民を増やし
| 23-086 |
|
トの道を教えた。トの教えを受けさせて治めた
【チヰモムラ】
1500の村。千五百(チヰモ)は多いことを表わす言葉として「数多く」とした。
【オオトシノ】
ヤマサカミの1人。豊穣の神。
| 23-089 |
|
東の方ではヒタカミから
| 23-090 |
|
治まって、その穏やかに治まった国の
| 23-091 |
|
たくさんの村にはそれぞれ長がいた。
【アワセテミチノ】
アシハラにも「チイモアキ」があり、数多くの村となった。ヒタカミとアシハラを合わせて3000。それで「非常に多く」とした。
【アメツチサリテ トオケレバ】
「アメ」は君(二尊)。「ツチ」は民。社会の仕組みが整ってくると、反面、君の思うことと民の意識の間に距離できてしまった。
| 23-094 |
|
遠くなって、自分勝手なことをする者が出てきた。
【モノノベヨモニ ツカワシテ アメマスヒトト ソヱフタリ】
物部は警察のような働きをし、アメマスヒト(地方長官のような役職)とソエ(副長官)二人で各地を治めた。
| 23-096 |
|
遣わして、アメマスヒトと
| 23-097 |
|
添え人二人を置いた。罪の程度を判断する