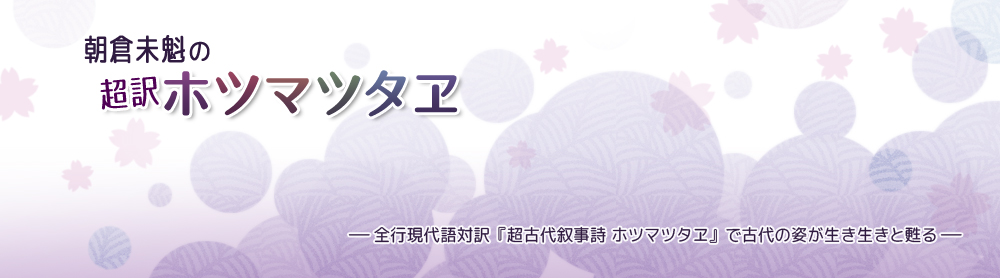先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【アワウワノ トフルミチビキ】
「アワウワ」は1綾本文003に、ワカ姫が育つ様子の中で「ツマノチオエテ アワウワヤ」と出てくるが、状況がまったく異なるので同じ意味の言葉ではないと考える。ここでは「アウワ」の音数を整えるために「ワ」が加えられたのではないか。「アウワ」はフトマニ図にある天の神、ミヲヤカミ、地の神を指すが、ここでは「全ての人々」の意と解釈した。
| 10-139 |
|
見事であった。また、タケミカツチは
| 10-140 |
|
出雲の平定において、まことに威厳があった。
【ナンタヤワラニ】
「ナンタ」は涙。「ヤワラニ」は柔らげる、服従させる。
【タマフカンヘハ】
「カンヘ」は「神部」と読んでよいと思うが、ここでは「称号、誉め名」という意味であろう。
| 10-143 |
|
『カシマカミ』の名を授けよう」。一方、服従した
| 10-144 |
|
オホナムチも百八十人の一族郎党を
| 10-145 |
|
連れてきて忠誠を尽くしており、これまでの出雲での善政にも
| 10-146 |
|
同情に値するものがあるとタカミムスビが
| 10-147 |
|
評価し、オホナムチにもそれなりの理があると認め、
【アソベノ アカルミヤ】
岩木山神社の祭神がオホナムチであることからも、岩木山の麓にあった宮と思われる。
【アフユ】
「ア」は天。ここではタカミムスビのこと。「フユ」は9綾解釈ノート155でふれた「神や天皇から授かるめぐみ深いたまもの」の意。「アフユ」はタカミムスビより与えられためぐみ深いたまものである領地。
| 10-150 |
|
オホナムチはアカルアソベの
【ウモトミヤ】
「ウ」は大きい。「モト」は「本」とか「元」というような意味と考えると、「大きな本宮」というような宮と考える。
【モモヤソヌヰノ シラタテニ】
「モモヤソ」は180。「ヌイ」縫う、貫く、のような意味で、たくさん連なっていることであろう。180人の人々がひとまとまりとなれるような新しい建物が数多くたてられ、それらが起伏のある土地での通路の役割を持つ懸け橋で結ばれていたのではないだろうか。「シラタテ」は次の文と二重に使われている。
【ウツシクニタマ】
オホナムチは出雲からツカルに国替えさせられたので「ウツシクニタマ」と言われた。
| 10-154 |
|
オホナムチは亡くなり、ツカルウモトの
【ホヒノミコトオ モトマツリ】
ホヒ尊はアマテルカミの皇子。オホナムチの御魂を出雲で祭った。
| 10-156 |
|
出雲の杵築神社の祭主とし、オホナムチを祭らせた。(後に)タカミムスビが
| 10-157 |
|
言われた。「汝、オホモノヌシの
| 10-158 |
|
クシヒコよ、国(出雲)の女性を娶ると、その者は
| 10-159 |
|
こちらの事がよくわからないだろう。我が娘のミホツ姫を
| 10-160 |
|
妻として、大勢の臣達を
| 10-161 |
|
まとめ、御孫のアスカホノアカリ尊をお守り
| 10-162 |
|
申し上げなさい」。この時賜ったヨロギの宮には
【ナメコトノ チクサヨロキ】
「ナメ」は「嘗め」と読み、貴人に薬を進める時、まず嘗めて毒見すること(広辞苑)と解釈し、「ナメコト」はその仕事、役目。「ヨロギノミヤ」は、薬効のあるたくさんの草木が植えてある薬用植物園ともいうべき宮だったのだろう。滋賀県の琵琶湖の西岸にある安曇川町にあったと言われている。
| 10-164 |
|
その草木を詳しく調べた。この宮の千草万木の薬効の知識を身につけ
| 10-165 |
|
世の中のために、病気を治す
| 10-166 |
|
道を拓いた。クシヒコには世継ぎが一人いて
| 10-167 |
|
名をヨロギマロミホヒコといい、その妻は
| 10-168 |
|
スヱツミの娘のイクタマヨリ姫で
| 10-169 |
|
十八人の男の子を産んだ。またコシ国のアチハセの娘の
| 10-170 |
|
シラタマ姫は十八人の姫を産んだ。
| 10-171 |
|
合わせて三十六人。たくさんの子ども達を育てるのに身をささげたので、
| 10-172 |
|
アマテルカミは詔を下し、コモリカミという
| 10-173 |
|
称え名を賜った。コモリカミはセミの小川で
| 10-174 |
|
禊ぎをし、茅の輪をくぐり身を清める神事を
| 10-175 |
|
毎年六月に行った。それは民の長寿を
| 10-176 |
|
願う祓いである。
| 10-177 |
|
「三代目大物主ヨロギマロミホヒコの御子の名の歌」
| 10-178 |
|
コモリカミの子の、長兄はカンタチ
| 10-179 |
|
次ツミハ、(三は)ヨシノミコモリ
| 10-180 |
|
四はヨテ、次はチハヤヒ、
| 10-181 |
|
(六は)コセツヒコ、七はナラヒコ
| 10-182 |
|
(八は)ヤサカヒコ、九はタケフツ
| 10-183 |
|
十はチシロ、十一はミノシマ
| 10-184 |
|
十二はオオタ、次はイワクラ
| 10-185 |
|
(十四は)ウタミワケ、(十五は)ツキノミコモリ
| 10-186 |
|
十六はサギス、次はクワウチ
| 10-187 |
|
(十八は)オトマロである。一姫はモト姫