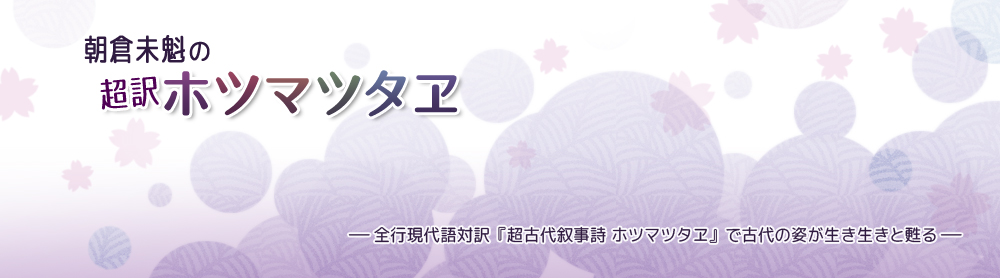先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【イセ】
「イモヲセ」「イモセ」と同じ。夫婦のこと。ここでの「イセ」は本文で述べられる「イセの道」のこと。「イセの道」とは、夫婦和合の教え。また「イセ」は伊勢の国も言う。
【スズカ】 「スズカ」と「スズクラ」と対比して出てくる。欲心を捨てること。
【スズカ】 「スズカ」と「スズクラ」と対比して出てくる。欲心を捨てること。
【タカノコフ ツボワカミヤ】
「タカノコフ」はヒタカミの都。「ツボ」はその要所、中心地。為政者のいる所。「ツボワカミヤ」は為政者であるヲシホミミの宮。
【アツキヒノ ヱラミ】
夏の特別暑い日に、ワカヒコはヲシホミミを見舞ったということか。「ヱラミ」は形容詞「豪い(程度が甚だしい、ひどい)」の語幹に、理由原因を表す接尾語「ミ」が付いたものとして「ひどかったので」と読み、「夏の日の暑さが甚だしかったので」と解釈した。
| 13-003 |
|
ワカヒコ(カスガマロ)に、ヲシホミミが酒を振舞って
| 13-004 |
|
言われた。「アマテルカミはイセの道に
| 13-005 |
|
ついて教え導かれた。吾はカスガに
【ハオナシ】
「ハ」は衣装のこと。自分の着ている衣装を整えたのであろう。
【マス】
「イマス」の縮まった語。「在す、坐す」と書き、在る、居る、行く、来るの尊敬語。神社に祭られている神にも「○○に坐す(マス)△△神」などという名もある。
| 13-008 |
|
続いてウオキミ(七代タカミムスビ)、カルキミの翁(オホナムチ)、
| 13-009 |
|
次にカトリカンキミ(カトリカミ)、及び
| 13-010 |
|
カシマキミ、ツクバ、シホガマ、
| 13-011 |
|
その他大勢が座った。さて、君の問は
| 13-012 |
|
「以前、吾が水浴びをしようとしたのを
| 13-013 |
|
ウオキミが止めて、水浴びのまねごとだけをしたが、
| 13-014 |
|
これはどういうわけなのか」。カスガが答えた。
| 13-015 |
|
「昔から伝わってきた教えによると、昔、ウビチニ尊が
| 13-016 |
|
ヒナガタケで三月三日に嫁いで
| 13-017 |
|
三日目に冷たい川で水浴びしました。
【ヒカワニアビル】
「ヒ」は氷雨などと使われるヒ。前行の「サムカワ」を冷たいとしたので、もっと冷たい「凍るような」とした。
| 13-019 |
|
この方々は強健だったからです。君はお体が優しく
| 13-020 |
|
柔らかでいらっしゃるので、ウオキミはそれをお考えになって
| 13-021 |
|
お止め申し上げたのでしょう」。
| 13-022 |
|
君は、「イセの道」について尋ねられた。カスガが説明申し上げた。
| 13-023 |
|
「夫婦には、この世のどんな家柄でも
【アメツチノノリ】
「天地の法則」は14綾や18綾に天地開闢に触れる記述があり、それを参照していただきたい。「アメツチノノリ」はこの時代の考え方の原理。概略は、この世が生まれたとき、「メ」と「ヲ」が生じた。「ヲ」は天、日、男(夫)、空・風・火で、それを「陽」とし、「メ」は地、月、女(妻)、水・土で、それを「陰」とする概念である。すなわち、天地の則は男女(夫婦)の則、日と月の則でもあり、それぞれの立場・役割があるということ。
【キミハアマテル ツキヒナリ】
この場合の「キミ」は君と后の二人をいう。二人が人々のために天下を治めること。
| 13-026 |
|
月と日です。国守はその
| 13-027 |
|
国を照らす月と日です。民も月と日なのです。
【メニホアリ】
「メ」(陰)の中には、本来陽である火もある。山火事などの自然の火は陽の火で、人が人工的に作り出した火は陰の火と考えていたようである。
【ヲニミツアリ】
「ヲ」(陽)の中に本来陰である水もある。炎の中心部の透明に近い部分を炎心といい、そこはまだ燃えていない気体・蒸気の部分。そこに物を入れると蒸気が付くことから炎の水と言ったのだろう。
| 13-030 |
|
燃えている炎の中の暗いところは
| 13-031 |
|
炎の水です。女と男の違いはあるけれども
【カミヒトツ】
「カミ」はさかのぼった方、源、おおもと。「アメツチノノリ」にある、空・風・火・水・土の5つの要素が混じってできたアメノミナカヌシが人類の初めと考えられていた。
【ヨヲトハヒナリ ヨメハツキ】 「ヨヲト」は良い夫・男、「ヨメ」は良い妻・女。
【ヨヲトハヒナリ ヨメハツキ】 「ヨヲト」は良い夫・男、「ヨメ」は良い妻・女。
| 13-033 |
|
よい妻は月です。月は元々
| 13-034 |
|
自ら光ってはいません。日の光を受けて
| 13-035 |
|
月は光っているのです。女と男もこれと同じです。
【ナカフシ】
15綾にも出てくるこの時代の宇宙観。地上から天界までの中ほどの所をいい、日はその外側を、月はその内側を巡っていると考えられていたのではないか。ミカサフミのタカマナルアヤ54行目から63行目に、太陽と月の軌道のことと思われる記述がある。そこに「ヒノメグリ ナカフシノトノ アカキミチ ヤヨロトメチノ ツキオサル ツキノシラミチ ヨヨヂウチ」と、本文と同じようなことが書いてある。
| 13-037 |
|
月は内側にあります。男は外での仕事に
| 13-038 |
|
務めるべきです。女は家の内を切り盛りし
| 13-039 |
|
布を織るのです。家長になるのは
| 13-040 |
|
兄だが、病気になったり親の
| 13-041 |
|
意に叶わなかったりした時は、弟に継がせて
【アコ】
我が子となるが、ここでは世継ぎとなる子。
| 13-043 |
|
家督を譲り受けます。仲人の仲立ちを得て結婚し
| 13-044 |
|
仲睦まじくし、子どもを産み育て、
【メハヨニスメル トコロエズ】
「女三界に家なし」という封建思想とは違うと思うが、男優位の考え方ではある。この時代、子どもを産み育てることは、きわめて重要なことであった。それには「家」は欠かすことのできないもので、そこで優しくいたわってくれる夫といることがよいということを言っていると理解したい。