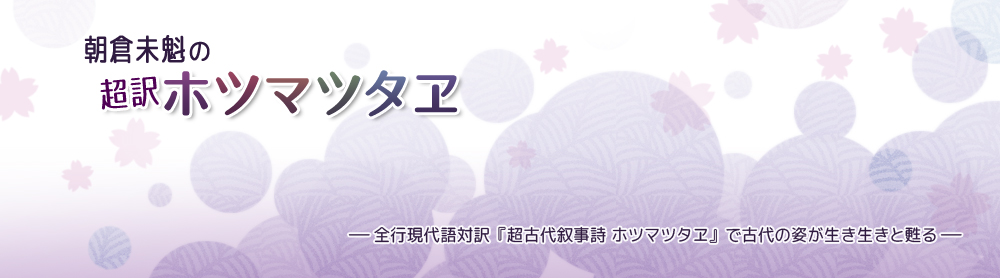先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【ササナミ】
琵琶湖にそそぐ安曇川の南に高島という地名がある。その辺りに「ササナミ」という所があったのだろうか。
【クマノヨロギノ】
滋賀県高島市の湖西線安曇川駅周辺に「西万木」という地名が残っているので、その辺りかと思われる。「クマノ」については不明。
| 24-106 |
|
田を拓こうとオオタとミシマに
| 24-107 |
|
井堰を築かせ、川を掘らせた。オトタマ川の
| 24-108 |
|
白砂の道に昼寝をしている
【チマタカミ】
広辞苑には「道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神」とあるが、物部達も恐れたというのであるから、ここではそのような存在ではない。正体不明な男というくらいの意味であろう。
| 24-110 |
|
顔はホオズキのように赤く、鼻の高さは七寸(キ)ほど、
| 24-111 |
|
目は鏡のようだった。供に付いていた八十人の物部達が
| 24-112 |
|
恐れたので、ニニキネがアメノウスメに
【メカチ】
難解な言葉であるが、この後のウズメの行動から、「見目勝ち」すなわち美貌、または「女(メ)勝ち」すなわち、女としての色気を前面に出すことではないか。
| 24-114 |
|
何者か聞いてまいれ」アメノウスメは胸をはだけて
| 24-115 |
|
裳の紐を下げて、声をたてて笑いながら近づいていった。
| 24-116 |
|
見知らぬ男は目を覚まして、「そのようなことをするのは
| 24-117 |
|
なぜか」と聞いた。アメノウスメは言った。「皇孫が
| 24-118 |
|
お通りになる先に、このようにしている汝こそ誰なのですか」
| 24-119 |
|
男が答えた。「アマテルカミの御孫が
| 24-120 |
|
お出でになるので、鵜川の仮宮で
| 24-121 |
|
宴でおもてなしをしようと、お待ちしていたナガタの
| 24-122 |
|
サルタヒコでございます」アメノウスメがまた尋ねた。
| 24-123 |
|
「どの道を行けばよいのですか」サルタヒコが答えて
| 24-124 |
|
「我がご案内しましょう」と言った。更に「汝は
| 24-125 |
|
我が君が行かれる所を御存じなのですか」と聞くと
| 24-126 |
|
サルタヒコが言った。「ニニキネ尊は筑紫の
| 24-127 |
|
高千穂にお出でになるのでしょう。吾は伊勢の南の
| 24-128 |
|
ナガタ川まで参ります。汝に、我の名を
| 24-129 |
|
ニニキネ尊に伝えていただければ、我も一緒に参りましょう」
| 24-130 |
|
アメノウスメはこの話をニニキネに伝えた。ニニキネは喜び
| 24-131 |
|
卯の花もまた飾って出発した。
| 24-132 |
|
サルタヒコに山道の大きな岩を
| 24-133 |
|
突き動かさせ、険しい道を切り開き
【ヨロイザキ】
この前後に出てくる地名は、現在も琵琶湖周辺に残っている。「鎧」のついた所はあることはあるが「ヨロイザキ」という地名は不明。したがってここはカタカナ表記とした。
【ミオノツチ】
「ミオ」は琵琶湖畔安曇川近辺に「三尾」と「水尾」とつく神社があり、「三尾里」という地名も残っている。「タケヤカガミノミオノツチ」の訳としては「タケ、カガミ、ミオの三つの土地の」と考える以外訳が考えられなかったが、「ノ」の扱いに無理がありそうに思う。地名も含めてより良い訳を考えていただきたい。土を積んだと言っても、山を築くほどではなく、儀式として使ったのではないか。36節の「ミオノチワキ」も三尾と岳山、鏡山の土をまとめて言っていると考える。
| 24-136 |
|
井堰を造った。ニニキネはサルタヒコに
| 24-137 |
|
ミオノカミの褒め名を与え、サルタヒコが好いたアメノウスメを
| 24-138 |
|
妻合わせた。そしてサルタヒコの名を表わす
【カクラオノコ】
現代でも神社で神に奉納する神楽は巫女が舞っているように、もとはアメノウスメなど、女が舞っていたのであろう。獅子神楽のように男が舞う神楽はこのサルタヒコに始まったのだろう。
| 24-140 |
|
君の祖である。
| 24-141 |
|
ニニキネが詔を下した。「三尾の土を積んで神を祭って開拓し、
| 24-142 |
|
田がここにできた。これは他の地の手本である。
| 24-143 |
|
この仮宮を瑞穂の宮と名付けよう」
| 24-144 |
|
その後、多賀の宮に行き、幣を奉げ、
| 24-145 |
|
美濃に行った。アマクニタマも一行が来たことを
【ムカシカスガニ ウルリヱテ ウムタカヒコネ】
「ウルリ」はそっくりなこと。ひとつは、昔カスガ命が婿に入ったこととタカヒコネが婿に来たこと、ひとつは、死んだ息子(アメワカヒコ)とタカヒコネが似ていたこと、この二つが掛けられている。それにちなみ、今でも美濃の特産になっているマクワウリを皆に配ったのだろう。
| 24-147 |
|
亡くなった息子とそっくりなタカヒコネを婿にできました。
| 24-148 |
|
そこで差し上げる物があります」と言って、各々にマクワウリを
| 24-149 |
|
一籠ずつ配ったので一行は喜んだ。
【シナノスワヨリ ミチビケバ】
美濃からハラミ山への道中、諏訪より差し向けられた道に詳しいものが道案内をしたと考える。
| 24-151 |
|
道案内されてハラミ山(富士山)に着いた。ハラミ山から
| 24-152 |
|
四方を見て「裾野は広い。
| 24-153 |
|
水を引いて、裾野を田にせよ」とニニキネは
| 24-154 |
|
タチカラヲに、裾野に水を引く井堰を掘らせた。