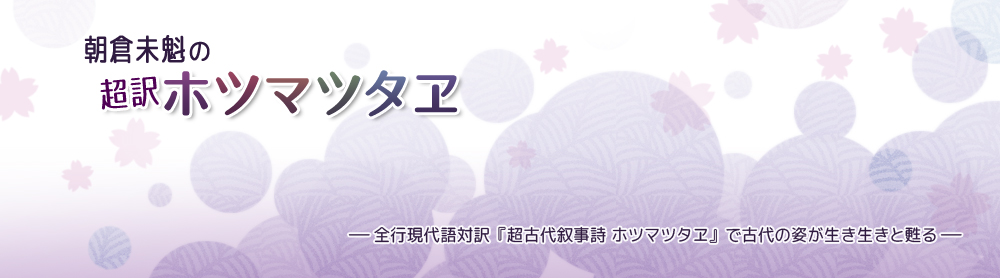先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【ハオナオハメハ チヨオウル】
ハオ菜を食べると「チヨオウル」で「モモニガシ」という文と、15綾本文155の「チヨミグサ ヨノニガナヨリ モモニガシ」とを合わせて考えると、ハオ菜と千代見草と同じものではないか。千代見草の葉が成長したものが「ハオ菜」で若芽のものを「ワカ菜」といったのだろう。
| 24-314 |
|
長生きできる。ワカ菜も同じように
| 24-315 |
|
苦いが、ハオ菜は
| 24-316 |
|
百倍も苦く、長寿の薬草だと教えても
| 24-317 |
|
民は食べない。ハオ菜の根は人の形をして、
| 24-318 |
|
葉はヨメナと同じ形で、花は八重に咲く。
【カブロバ】
15綾本文128に「ススシロ」として蕪が書かれているが、蕪は「カブラ」ともいい、葉の部分が、栄養価が高いことを考えると、蕪の葉と考えてもよいのではないか。
| 24-320 |
|
血を増やし、年寄りも若返る。
【ワカムスビ コノコオクワニ】
5綾本文045に「ワカムスビ クビハコクワニ ホゾハゾロ コレウケミタマ」とある。この場合は、「ワカムスビ」は蚕を修飾する言葉。「コノ」が何を指すか不明。音数を整えるためか。
【コキリヒメ】
ココリ姫のこと。キクキリ姫、シラヤマ姫ともいう。
【コヱネノクニ】
2行後に「コヱニキテ」、本文337に「コヱクニ」とあり、紛らわしいが、「コヱクニ」は関東・東海地方を指す。「コヱネ」と「コヱニキテ」の「コヱ」は「コヱクニのネ(北)の方の国」で北陸地方の「ネの国」。コキリ姫はネの国の人。
| 24-324 |
|
大物主のコモリが北の国から巡り歩いて
| 24-325 |
|
ネの国に来て、以前ニニキネの御衣裳に描いた絵を織るように勧めた。
| 24-326 |
|
コキリ姫はその模様を綾織りの
| 24-327 |
|
鳥襷にしてアマテルカミに差し上げた。
【ニシノ ハハ】
ココリ姫の義妹のウケステメのこと。そのことは本文087以降に書かれている。
| 24-329 |
|
その鳥襷は、後世まで残った。大物主がタガの国に行くと
【ツエガツマ アサヒメ】
アサ姫はコモリの娘。ツエはその夫だが、詳細は不明。
| 24-331 |
|
大物主は、桑がよく育っているのを見て
【コカイキヌオル タチヌイノ ミチオシユレバ】
コモリは供の者を連れていて、その中の技術者が教えたのであろう。
| 24-333 |
|
裁縫の方法を教えた。
【ヲコタマノ カミオマツリテ】
「ヲコタマ」はコモリの親のオオクニタマ。
| 24-335 |
|
しばらく静養をした。大物主が裁縫用の物差しを作って
| 24-336 |
|
裁縫の方法を民に教えたので
| 24-337 |
|
それが一帯に普及し、大物主はコヱ国のカミと言われ
| 24-338 |
|
オオクニタマの里は養蚕が盛んになった。
| 24-339 |
|
ニニキネがまたハラミ山を巡り歩いた時
| 24-340 |
|
寝冷えをして腹が痛くなった。
| 24-341 |
|
コモリが山に生えている薬草を飲ませて
| 24-342 |
|
腹痛を治した。それは人の体によくなじむ
【ネハコネウスギ…】
ここから3行はヒトミ草の形態を説明しているようだが、分かりにくい。「コネ」は「小さい根」としたが、根があまり張らないようなことなのか確信はない。「ヒトリ」の「 」は数詞なので「1」、「トリ」または「リ」が分からないが、「ヨエイハ」は4本の枝と5枚の葉と考えられるので、「ヒトリ」を「1本の茎」とした。「ヒトミ」は「ヒトミ草」と名付けられた理由となる言葉だが、これまでの形態の説明では、「一枝五枚の葉が掌に見える」というくらいしか思いつかない。想像たくましく「コシロハナ」を頭状花として、それを頭部、4本の枝を手足、5枚の葉をそれぞれの指として、人の体に見立てたと考えてみた。
| 24-344 |
|
一本の茎に四本の枝があり、五枚の葉が付き、人の体のように見える。
| 24-345 |
|
小さな白い花を付け、秋には小豆のような実が付く。
| 24-346 |
|
味は甘苦く、手足を潤し
| 24-347 |
|
気分をよくする。薬草はいろいろあるが
【ハラミノミ】
3種類の薬草は、千代見草、葉桑、ヒトミ草。
【ハラミヤマナリ】
訳文では「ハラミ」の持つ意味がわからないが、腹痛を治したことを言って「腹(病み)止み山」としたのか、3種類(ミ)の「ラ草」の葉(ハ)の薬効が素晴らしいと言ったのか、そのような意味を持たせた「ハラミ」ではないか。
| 24-350 |
|
二尊が国を治めた時の政の中心地は
| 24-351 |
|
オキツボ(近江)であった。アマテルカミは、
| 24-352 |
|
ヒタカミの政の中心地の
【ケタツボノフミ】
「ケタツボ」はヒタカミ。ヒタカミでアマテルカミがトヨケから学んだ帝王学。
【ヰツカミノ ハラミハツボハ】
「ハラミハツボ」は初めアマテルカミが政を執った場所だが、ニニキネの新田開発などにより「四方八方」の中心地となった、と解釈し「ヰツカミ」はニニキネ。二尊とニニキネにはさまれたアマテルカミの政治の中心地についての記述がないのがやや気になるが、ここはニニキネのことを述べているので省略したのだろう。
| 24-355 |
|
国中の政の中心地であった。
【ヲキミ】
「ヲ」を治めるという意味も持つ「御」とし「ヲキミ」を「御君」と訳した。
| 24-357 |
|
という称号を授けた。新治の民が、自分たちは