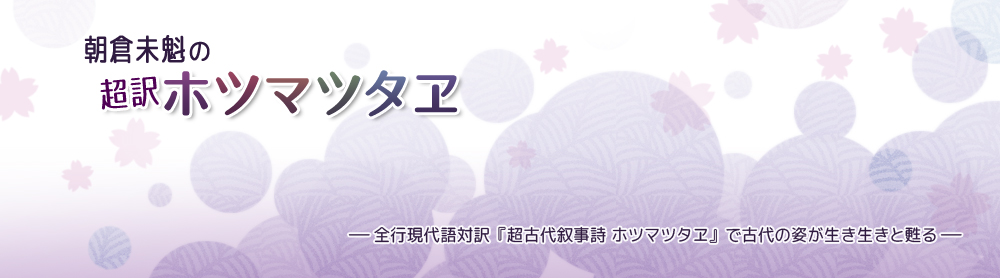先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【ウミノナモ】
山中湖からスト湖までの八湖に井堰を造り、水を引いたのであろう。現在の富士五湖ができた時代は西暦800年から860年と言われているので、古山中湖があったと言われるように、現在ある山中湖、河口湖、本栖湖もこの時代のものとは規模や位置が違うのではないか。
| 24-156 |
|
東北はアス湖、北は川口湖、
| 24-157 |
|
北西は本栖湖、西は西の湖、
| 24-158 |
|
西南はキヨミ湖、南はシビレ湖、
| 24-159 |
|
東南はスト湖である。新治の民が
| 24-160 |
|
大勢やってきて、それぞれの湖の土を持ち寄り
【ミネニアゲ】
富士山頂まで儀式用の土を運んだとも考えたが、このあとに「ナカノワモガナ」とあり、実際の富士山頂の噴火口に土を盛ることは不可能なので、富士山を模した儀式用の小山を造ったと解釈した。
【ヤブサハカリト アニコタエ】 「ヤフサ」は八房飾りとも富士八峰とも考えられるが、話のつながりから「八峰」とした。「ハカリ」は「~程の」と解釈した。さらに八峰だけでなく、一大事業の成功を願い、より天の神に近づけるように、真ん中にも峰を造ろうとしたのではないか。
【ヤブサハカリト アニコタエ】 「ヤフサ」は八房飾りとも富士八峰とも考えられるが、話のつながりから「八峰」とした。「ハカリ」は「~程の」と解釈した。さらに八峰だけでなく、一大事業の成功を願い、より天の神に近づけるように、真ん中にも峰を造ろうとしたのではないか。
| 24-162 |
|
天に願いが届くようにし、真中の峰も欲しいものだと考えて、
【ウツロヰガ アワウミサラエ】
「ウツロヰ」は21綾本文230で、新治の宮での騒動の末、ニニキネより「ウツロヰノヲマサギミ」と名を与えられた者。新治の民と共にやってきたのであろう。どの程度の土を運んだのかは分からないが、ウツロヰ達が運んだのは儀式に用いる程度ではないか。
| 24-164 |
|
三尾の土を担いで運び、
| 24-165 |
|
短期間のうちに真中の峰を造り上げた。
【ヰヅアサマミネ】
「アサマ」は富士山麓にある浅間神社となったのであろうが、ここでは「朝の間」に造ったということから、敢えて「朝間」と訳した。
| 24-167 |
|
山は高く、湖は深く
| 24-168 |
|
他に並ぶ所はない。ハラミ山の峰に降る雪は
| 24-169 |
|
湖の水となり、流れの末は多くの里の
| 24-170 |
|
田となって、あまたの民を潤した。
| 24-171 |
|
「二十年毎に井堰を浚え」と言って
| 24-172 |
|
ニニキネは酒折りの宮に入った。
| 24-173 |
|
酒折りの宮の留守をあずかっていたオオヤマスミが
| 24-174 |
|
宴を開いた。御膳を差し上げた
| 24-175 |
|
アシツ姫をニニキネは一夜召して
| 24-176 |
|
妻とした。ニニキネは新治の宮に帰って
| 24-177 |
|
ユキ宮スキ宮を建てて祈り
| 24-178 |
|
大嘗祭を行った。三種の宝を引き継いだことを
| 24-179 |
|
天の神に告げ、三種の宝を宮に納めた。
| 24-180 |
|
その飾りは香久の木と八幡であった。
| 24-181 |
|
その次の日には民に
| 24-182 |
|
即位した姿を拝謁させた。アマノコヤネは鹿島で
| 24-183 |
|
年を越した。大物主のコモリは一人で
| 24-184 |
|
日高見の井堰を造りながら、
| 24-185 |
|
日隅に行った。祖父のオホナムチは喜び
| 24-186 |
|
「汝の父クシヒコが大和で亡くなった
| 24-187 |
|
後、孫の汝に会いたく思いながらも
| 24-188 |
|
歳をとってしまった」と言って自ら宴を催した。
| 24-189 |
|
大物主も喜んで言った。
【ヤマオヤフサノ ヰユキナス】
分かりにくい表現だが、「ヤフサノヰユキ」を「富士山に積もった雪がとけて流れる水」と解釈して意訳をした。その壮大な仕事にオオナムチは驚いたのだろう。
| 24-191 |
|
雪の水で田を拓きました」オホナムチは驚いて
| 24-192 |
|
「我は同じように、新田を拓いてきたけれど、
【コケシラス】
「コケ」の意味不詳。他の写本に「コレ」とあるのでそれを採用する。
| 24-194 |
|
世の中を良くする君である。君は末々までもの御親である。
| 24-195 |
|
ニニキネ尊によく尽くしなさい」と言って、国境まで
| 24-196 |
|
送っていき、名残りを惜しんだ。
| 24-197 |
|
大物主は海伝いに西の方へ
| 24-198 |
|
巡りながら、工事の絵図を作り、新田を
| 24-199 |
|
造らせた。佐渡にも渡って
| 24-200 |
|
新田を造り、また越の国に戻って
| 24-201 |
|
井堰を造った。
| 24-202 |
|
さて、ニニキネは思うことがあり
| 24-203 |
|
アマノコヤネを新治の宮に残して
| 24-204 |
|
カツテに、海沿いの道を行く
| 24-205 |
|
行幸の触れを出させた。オオヤマスミは
| 24-206 |
|
伊豆の岬の仮宮にニニキネをお迎えし
| 24-207 |
|
宴を催した。御膳を差し上げている時