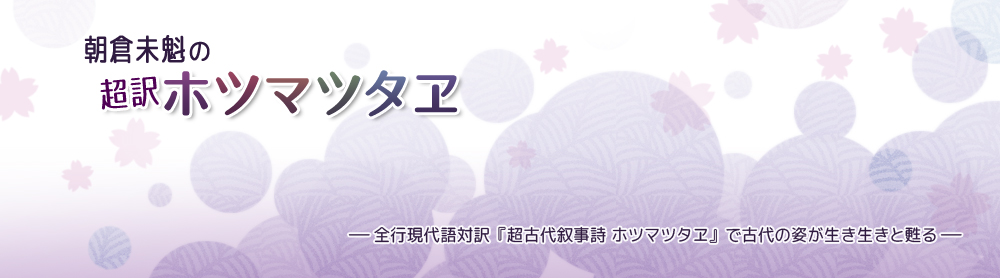先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【メツム】
「愛づむ」と読んで、「感嘆する、感心する」と解釈した。
| 39-333 |
|
天気がよかったが、一月二十八日に
| 39-334 |
|
大雪が降ったので、君は橇に乗られて
| 39-335 |
|
相模の館に行き、館に
| 39-336 |
|
入られた。野に鐙の片方が落ちているのを
| 39-337 |
|
トラガシハが拾って、君にどのようにして渡そうかと考え、
| 39-338 |
|
鐙に玉飾りを付けて君のもとに
| 39-339 |
|
届けた。ヤマトタケがそれを褒めて
| 39-340 |
|
その村の名をタマガワアブミと名付けて与え、
| 39-341 |
|
武蔵の国と相模の国とを
【ナヅケタマワル】
ここは文が交錯しているように思う。村の名前をタマガワアブミと名付け、トラガシハに与え、カグモトヒコを武蔵の国と相模の国の国守とした、ということ。だが、カグモトヒコは元々相模の国の領主であったはずなので、先の戦いの後、改めてヤマトタケの配下になった者への任命なのだろうか。
【マチカテチカ】
本文083でヲトタチバナ姫に随行し、相模の小野の城で守りを固めたホツミテシとサクラネマシ。
| 39-344 |
|
二人の臣はヲトタチバナ姫の
【クシトオビ ウレバ】
姫を守っていたホツミテシとサクラネマシが姫の櫛と帯をどのようにして得たのか。船に残された遺品なのか、姫が身に着けていたものが流れ着いたのか、果てしてどちらなのだろうか。
【ツカリアビキ】
「ツカリ」は「連り(ツガリ・ツカリ)」と読み、「連なり続くこと」の意から「縁のある」と解釈し、ヲトタチバナ姫と縁のある二人が姫の魂を天に導く祭りと考える。また「ツカリ」を「塚を造り」と読むと、「カタミオココニ ツカトナシ」の「ツカ」とつながるようにも思う。
| 39-347 |
|
祭りをした。これはソサノヲが
| 39-348 |
|
大蛇(ハヤコ姫)を縁によって、ヤスカタ
【ハヤスヒヒメモ アシナヅチ ナナヒメマツル】
「ハヤスヒ姫」は7綾本文079にアカツチの娘の「ハヤスフ姫」として出てくる。28綾のシマツウシの話で、ハヤスヒ姫はハヤコに殺されたことがわかる。同じく28綾本文295にはアカツチの弟のアシナヅチの8人の娘のうち7人までがハヤコ姫に殺されたと書かれている。これは9綾本文007でソサノヲがサスラになって訪ねた先でのできごとのことである。これらの姫たちを「ツカリ」すなわち縁によって祭ったという前例にならったということ。
| 39-350 |
|
アシナヅチの七人の姫を祭ったことを
| 39-351 |
|
前例としたのである。ヲトタチバナ姫の形見をここに
【アツマモリ】
「吾夫守」と読むと、夫のヤマトタケを守ろうと身を投げたヲトタチバナ姫を表しているように思える。
| 39-353 |
|
大磯に社を建てて
| 39-354 |
|
ヲトタチバナ姫の霊を祭り、マチカとテチカはこの地に留まった。
| 39-355 |
|
ハナヒコ(ヤマトタケ)は、自分の先御魂を
| 39-356 |
|
自覚され、カワアイの野に
| 39-357 |
|
大宮を建て、
| 39-358 |
|
氷川神(ソサノオ)を祭らせた。武具は
| 39-359 |
|
秩父の山に納めた。二月八日に
| 39-360 |
|
国々を巡り、服従した印に
| 39-361 |
|
香久の枝を立てた籠を屋根の棟に捧げさせ
| 39-362 |
|
戦を終わらせた。これはホツマの国に広く伝わる
| 39-363 |
|
習わしとなった。碓氷峠の坂で
| 39-364 |
|
ヤマトタケは死に別れたヲトタチバナ姫を
【キサオノゾミテ】
碓氷峠から東南の方角にヲトタチバナ姫が身を投げた大磯から上総へ行く相模灘が位置する。
| 39-366 |
|
姫を忍んで形見の歌札を
| 39-367 |
|
取り出して見た。
【サネサネシ】
大辞林には、古事記の「サネサシ」を出典として「さがむ(相模)にかかる。語義・かかり方未詳」とある。私は「サネ」を「実」と読み、「物事の中核となるもの、根本のもの」ということから、人の理想的な姿、ここでは雄々しい姿と解釈した。
| 39-369 |
|
炎に包まれているその火の中に立って
| 39-370 |
|
訪ねて来てくださった君は」
【アヅマアワヤ】
7綾本文146のワザオギの歌に「アガツマアワヤ」という言葉が出てくる。そこでは「我が妻は天地だ」と訳した。それは、妻は我の全てだというようにも言い換えられると思う。この場面でもヤマトタケは「ヲトタチバナ姫は自分のすべてだった」と嘆いたのではないか。
| 39-372 |
|
嘆いた。これがこの地を「吾妻」と呼ぶ謂われである。
| 39-373 |
|
追分でキビタケヒコには
| 39-374 |
|
越路を行かせ、越の国の様子を
| 39-375 |
|
見させた。タケヒを先に
| 39-376 |
|
相模から蝦夷の土産を
| 39-377 |
|
持って都へ帰らせ、帝に捧げて
| 39-378 |
|
蝦夷がことごとく服従した様子を
| 39-379 |
|
報告させた。二人と別れ一人になった
| 39-380 |
|
ヤマトタケは一行を連れて進んだ。信濃の木曽路は
| 39-381 |
|
山が高く谷は深く