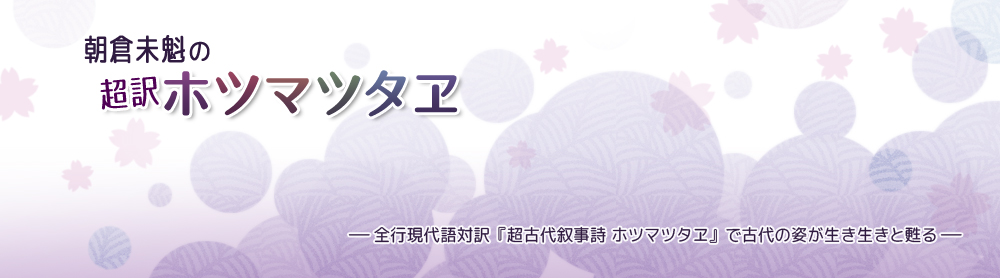先頭の番号が青い行は、クリックすると解釈ノートが見られます。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
対訳ページの使い方の詳細はこちらのページをご覧ください。
【キミトミ】
「キミ」はアマテルカミ、「トミ」はカスガ(アマノコヤネ)。
| 28-001 |
|
五十スズ、千枝、二十年。
| 28-002 |
|
君が代わったのに、新しい暦がまだできていないので
【イセニモフデテ】
伊勢にいるのは4行後に出でくるカスガだが、訪ねて行った先は伊勢にいるアメフタヱ。
【フタヱコレヨリ ウカガハデ】
「コレ」は天君が代った時を指す。
【ウカガハデ】
アメフタエは、君が代ったので暦について相談しに多賀に行かなければならないと思っていた。タケヒトは君を継いだが筑紫にいたので、多賀の御君イツセが左右の臣のオシクモと大物主のいる多賀で政を執っていた。
【コフトノニウク】 「コフトノ」は多賀。「ウク」は受ける、すなわち来てもらうこと。
【コフトノニウク】 「コフトノ」は多賀。「ウク」は受ける、すなわち来てもらうこと。
| 28-006 |
|
喜び、共に
| 28-007 |
|
伊勢のオウチ宮に行った。カスガに会って
| 28-008 |
|
スズキ暦の成り立ちを聞いた。カスガは次のように答えた。
| 28-009 |
|
「このスズキ暦は天地開闢の頃、
| 28-010 |
|
クニトコタチが宮にマサカキを植えたのが始まりです。
【アヱ】
直訳すれば「天の枝」。「ア」は美称か。
| 28-012 |
|
植え継いで五百本になると
【ミモハカリ】
1ハカリが10万。
| 28-014 |
|
五百一本目のマサカキの
| 28-015 |
|
一年目に出た穂は、十年で五寸、
| 28-016 |
|
六十年で三咫伸びて、それがヱトの
| 28-017 |
|
一巡りとなります。新しい年が始まって
| 28-018 |
|
三咫枝が伸びると、ヱトが二回り目となり
| 28-019 |
|
またキアヱから枝と穂を数えます。
| 28-020 |
|
一枝が六十年、十枝で六百年、
| 28-021 |
|
百枝で六千年、千枝では六万年となるように
| 28-022 |
|
暦の守はヱトを一巡りずつさせて
| 28-023 |
|
暦を作ります。ですから、千枝の年に
| 28-024 |
|
マサカキの種を植え、次の年に芽が出るようにします。
| 28-025 |
|
はじめ、マサカキをハコクニ宮に
| 28-026 |
|
クニトコタチが植えて、国の名を
| 28-027 |
|
ヒタカミとし、それをタカミムスビが
| 28-028 |
|
植え継ぎました。二十一スズの
| 28-029 |
|
百枝の後に五代タマキネ尊の娘の
| 28-030 |
|
イサコ姫は七代目の君の
| 28-031 |
|
タカヒト君とヒタカミの西南の
| 28-032 |
|
筑波山より流れ出るイサ川の
| 28-033 |
|
宮で結婚を承諾して
| 28-034 |
|
二人は結ばれました。名もイサナギ尊と
| 28-035 |
|
イサナミ尊となり、アメフタカミと言われました。
| 28-036 |
|
二尊は世継ぎがいなかったので、タマキネ尊が
| 28-037 |
|
カツラキの山で祈ると、
| 28-038 |
|
アメミヲヤが日輪の御魂を
| 28-039 |
|
分け下して、イサナミ尊はアマテルカミを
| 28-040 |
|
お生みになりました。それは二十一スズ、
| 28-041 |
|
百二十五枝、三十一年、キシエの日の
| 28-042 |
|
日の出の時でした。若日(初日)と一緒に
| 28-043 |
|
お生まれになったので、諱をワカヒトと名付けました。
| 28-044 |
|
産宮はハラミ山の酒折の宮でした。
| 28-045 |
|
皇子の胞を北の方角に納めると
| 28-046 |
|
胞衣は皇子をよく守り、災いがある時でも
| 28-047 |
|
事態を覆して防ぎ、災いを払い、
| 28-048 |
|
災いは鎮まり、皇子は長生きをする
| 28-049 |
|
ということで、オオヤマスミ命が
【ヨメヂユクネノ】
「ヨメヂ」の語義不詳だが、漢字で「良目路」と読むと、「良目(見た目の良いさま)」の路となる。胞衣を納めるにふさわしい良い場所を探して着いた峰と訳せるのではないか。また「夜目路」と読むと、日が暮れてから北極星を頼りに、胞衣を納める北の方角を見定めたというようにも解釈できる。また少々突飛かもしれないが、長い距離を表す「トメジ」を当てはめて、そのころの距離感での「四(ト)メジもの距離を歩いた」とすることもあり得ないだろうか。
【ヱナガタケ】
長野県の恵那山か。